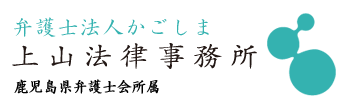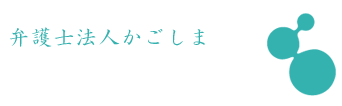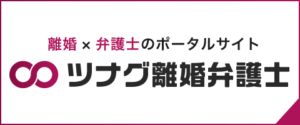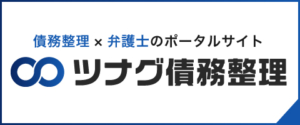労災事故に遭われた方
当事務所では、残業代未払い等の残業代請求等も積極的に取り扱っておりま
当事務所では、労災事故、過労自殺等も取り扱っております。
労災事故は、労災保険給付請求の後、使用者に安全配慮義務違反が存する場合、安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求(労災民訴)を行い、損害の回復を行わなければなりません。
1 労災保険
労災保険は、大別して、保険事故・原因別に、業務災害(仕事、業務上によるもの)と通勤災害(通勤によるもの)に対する保険給付の二つからなります。
(1)業務災害とは
業務災害とは、労働者が、業務を原因として被った負傷、疾病または死亡をいいます。業務災害に対する保険給付は、労働者が労災保険の適用される事業場に雇われて、事業主の支配下にあるときに、業務が原因となって発生した災害に対して行われます。
ア 業務上の負傷について
業務上の負傷といえるか否かは、①業務遂行性と②業務起因性の二つの要件を満たすか否かにより判断されます。
①業務遂行性とは、労働者が事業主の支配ないし管理下にあるなかでという意味であり、②業務起因性とは、業務又は業務行為を含めて労働者が労働契約に基づき事業主の支配下にあることに伴う危険が現実化したものと経験則上認められることをいうとされています。
業務遂行の有無を判断し、その上で、業務起因性が判断されます。
一般的に、業務遂行性が認められる災害(負傷、疾病、死亡等)は、次の3つに大別されます。
① 事業主の支配下にあり、かつその管理下にあって業務に従事している際に生じた災害。要するに、事業場内で作業に従事中の災害(業務遂行性が認められるパターン①)。
この場合、原則として、業務起因性は認められます。もっとも、自然現象(ただし、自然現象や外部の力も当該職場に定型的に伴う危険であれば業務起因性は認められます)、本人の私的逸脱行為、規律違反行為(酒に酔って作業等)などによる場合は業務起因性が認められません。
② 事業主の支配下にあり、かつその管理下にあるが、業務には従事していないときの災害。要するに、事業場内での休憩中や始業前、終業後の事業場内での行動の際の災害(業務遂行性が認められるパターン②)。
この場合、労働時間中であれば業務起因性があるものや事業場施設の不備、欠陥によるものでなければ業務起因性は認められません。
③ 事業主の支配下にあるが、その管理を離れて、業務に従事している際の災害。要するに、事業場外で労働しているときや出張中の災害(業務遂行性が認められるパターン③)。
この場合、危険にさらされる範囲が広いので、業務起因性は広く認められます。しかし、積極的な私的行動による災害は業務起因性が否定されます。
イ 業務上の疾病について
業務上疾病とは、労働者が事業主の支配下にある状態において発症した疾病ではなく、事業主の支配下にある状態において有害因子にさらされたことによって発症した疾病をいいます。
一般的に、次の3要件が満たされる場合に、原則として業務上疾病と認められます。
① 労働の場に有害因子が存在していること
業務に内在する有害な物理的因子、化学物質、身体に過度の負担のかかる作業、病原体などの諸因子を指します。
② 健康障害を起こしうるほどの有害因子にさらされたこと
健康障害を起こすに足りる有害因子の量、期間にさらされたことが認められなければなりません。
③ 発症の経過および病態が医学的にみて妥当であること
業務上の疾病は、労働者が業務に内在する有害因子に接触することによって起こるものなので、少なくともその有害因子にさらされた後に発症したものでなければなりません。
(2)通勤災害とは
通勤災害とは、通勤によって労働者が被った傷病等をいいます。
この場合の「通勤」とは、①「就業に関し」、②「住居」と③「就業の場所」との間の往復、就業の場所から他の就業の場所への移動、単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を、④「合理的な経路および方法」で行うことをいい、⑤「業務の性質を有するもの」を除くとされています。⑥「移動の経路を逸脱し、または中断した場合」には、逸脱、または中断の間およびその後の移動は「通勤」となりません。ただし、例外的に認められた行為で逸脱または中断した場合には、その後の移動は「通勤」となります。
ア 「就業に関し」とは
通勤は、その移動が業務と密接な関連をもって行わなければなりません。
したがって、住居と就業の場所との間の往復、就業の場所から他の就業の場所への移動の場合、被災当日に就業することとなっていたこと、または現実に就業していたことが必要です。なお、通常の出勤時刻とある程度の前後があっても就業との関連性は認められます。
また、単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動の場合、原則として、就業日とその前日または翌日までに行われるものについて、通勤と認められます。
イ 「住居」とは
「住居」とは、労働者が居住している家屋などの場所で、本人の就業のための拠点となるところをいいます。
ウ 「就業の場所」とは
「就業の場所」とは、業務を開始し、または終了する場所をいいます。
エ 「合理的な経路および方法」とは
「合理的な経路および方法」とは、移動を行う場合に、一般に労働者が用いると認められる経路および方法をいいます。
「合理的な経路」については、通勤のために通常利用する経路が、複数ある場合、それらの経路はいずれも合理的な経路となります。また、当日の交通事情により、迂回した経路、マイカー通勤者が駐車上を経由して通る経路など、通勤のためにやむを得ず通る経路も合理的な経路となります。
「合理的な方法」については、通常用いられる交通方法(鉄道、バスなどの公共交通機関を利用、自動車、自転車などを本来の用法に従って使用、徒歩など)は平常用いているかどうかにかかわらず、合理的な方法となります。
オ 「業務の性質を有するもの」とは
①から④までの要件を満たす移動であっても、その行為が「業務の性質を有するもの」である場合には、通勤となりません。
具体的には、事業主の提供する専用交通機関を利用して出退勤する場合や緊急用務のため休日に呼び出しを受けて出勤する場合などの移動による災害は、通勤災害ではなく業務災害となります。
カ 「往復の経路を逸脱し、または中断した場合」とは
「逸脱」とは、通勤の途中で就業や通勤と関係のない目的で合理的な経路をそれることをいい、「中断」とは、通路の経路上で通勤と関係のない行為を行うことをいいます。
通勤の途中で逸脱または中断があるとその後は原則として通勤とはなりませんが、これについては、日常生活上必要な行為であって、下記に該当するやむを得ない事由により最小限度の範囲で行う例外的な場合には、逸脱または中断の間を除き、合理的な経路に復した後は再び通勤となります。
【逸脱中断の例外となる行為】
① 日用品の購入その他これに準ずる行為
② 公共職業能力開発施設において行われる職業訓練、学校において行われる教育その他これらに準ずる教育訓練であって職業能力の開発向上に資するものを受ける行為
③ 選挙権の行使その他これに準ずる行為
④ 病院または診療所において診察または治療を受けること、その他これに準ずる行為
⑤ 要介護状態にある配偶者、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹並びに配偶者の父母の介護(継続的にまたは反復して行われるものに限る)
(3)労災保険給付の内容
ア 療養補償給付
業務災害または通勤災害による傷病により療養するときに給付されます。
必要な療養の給付(労災病院や労災保険指定医療機関等以外で療養を受けたときは、必要な療養の費用の支給)がなされます。
イ 休業補償給付
業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないときに給付されます。
休業4日目から、休業1日につき給付基礎日額(平均賃金に相当する金額)の60%相当額が支給されます。
また、上記休業補償給付に加えて、社会復帰促進等事業の一つとして、休業4日目から、1日につき、給付基礎日額の100分の20に相当する休業特別支給金が支給されます。
そのため、休業期間中の補償は、合計で給付基礎日額の80%相当額が補償されることとなります。
ウ 障害補償給付
障害の程度に応じて、遺族補償年金として支給されるのか、遺族補償一時金として支給されるのか異なります。
(ア)障害補償年金
業務災害または通勤災害による傷病が症状固定した後に、障害等級第1級から第7級までに該当する障害が残ったときに支給されます。
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から131日分の年金が支払われます。
第1級 313日分 第5級 184日分
第2級 277日分 第6級 156日分
第3級 245日分 第7級 131日分
第4級 213日分
また、上記障害補償年金に加えて、社会復帰促進等事業の一つとして、障害の程度に応じ、342万円から159万円までの障害特別支給金が一時金として支払われます。加えて、上記障害補償年金の給付基礎日額には、賞与等3か月をこえる期間の賃金は算入されないので、賞与等3か月をこえる期間の賃金(特別給与)分を上積みする趣旨で、障害の程度に応じ、算定基礎日額の313日分から131日分の年金が支払われる障害特別年金が設けられています。
(イ)障害補償一時金
業務災害または通勤災害による傷病が症状固定した後に障害等級第8級から第14級までに該当する障害が残ったときに支給されます。
障害の程度に応じ、給付基礎日額の503日分から56日分の一時金が支払われます。
第8級 503日分 第12級 156日分
第9級 391日分 第13級 101日分
第10級 302日分 第14級 56日分
第11級 223日分
また、上記障害補償一時金に加えて、社会復帰促進等事業の一つとして、障害の程度に応じ、65万円から8万円までの障害特別支給金が一時金として支払われます。加えて、上記障害補償一時金の給付基礎日額には、賞与等3か月をこえる期間の賃金は算入されないので、賞与等3か月をこえる期間の賃金(特別給与)分を上積みする趣旨で、障害の程度に応じ、算定基礎日額の503日分から56日分の一時金が支払われる障害特別一時金が設けられています。
エ 遺族(補償)給付
遺族補償年金として支給されるのが原則ですが、例外的な場合には遺族補償一時金として支給されます。
(ア)遺族(補償)年金
業務災害または通勤災害により死亡したときに支給されます。
遺族の人数に応じ、給付基礎日額の245日分から153日分の年金が支払われます。
1人 153日分
2人 201日分
3人 223日分
4人以上 245日分
また、上記遺族補償年金に加えて、社会復帰促進等事業の一つとして、遺族特別支給金300万円(遺族の数にかかわらず、一律)が支払われます。加えて、上記遺族補償年金の給付基礎日額には、賞与等3か月をこえる期間の賃金は算入されないので、賞与等3か月をこえる期間の賃金(特別給与)分を上積みする趣旨で、遺族の数に応じ、算定基礎日額の245日分から153日分の遺族特別年金が支払われます。
(イ)遺族(補償)一時金
業務災害または通勤災害により死亡したときで、次のいずれかに該当する場合に支給されます。
①遺族補償年金を受け得る遺族がいないとき
②遺族補償年金を受けている人が失権し、かつ、他に遺族補償年金を受け得る人がない場合であって、すでに支給された年金の合計額が給付基礎日額の1000日分に満たないとき
給付基礎日額の1000日分の一時金(上記②の場合は既に支給した年金の合計額を差し引いた金額)が支払われます。
また、上記遺族補償一時金に加えて、社会復帰促進等事業の一つとして、遺族特別支給金300万円(遺族の数にかかわらず、一律)が支払われます。加えて、上記遺族補償一時金の給付基礎日額には、賞与等3か月をこえる期間の賃金は算入されないので、賞与等3か月をこえる期間の賃金(特別給与)分を上積みする趣旨で、遺族の数に応じ、算定基礎日額の1000日分の一時金(上記②の場合は既に支給した遺族特別年金の合計額を差し引いた金額)が支払われます。
オ 葬祭料
業務災害または通勤災害により死亡した人の葬祭を行うときに支給されます。
31万5000円に給付基礎日額の30日分を加えた額(その額が給付基礎日額の60日分に満たない場合には、給付基礎日額の60日分)が支給されます。
カ 傷病(補償)年金
業務災害または通勤災害による傷病が療養開始後1年6か月を経過しても治っていない場合であって、1年6か月を経過した日において当該負傷・疾病による障害の程度が1級~3級(全部労働不能)の程度に達している場合に、その状態が継続している間支給されます。
障害の程度に応じ、給付基礎日額の313日分から245日分の年金が支給されます。
第1級 313日分
第2級 277日分
第3級 245日分
上記傷病補償年金に加えて、障害の程度により、傷病特別支給金として、114万円から100万円までの一時金及び、傷病特別年金として算定基礎日額の313日分から245日分の年金が支給されます。
キ 介護(補償)給付
障害(補償)年金または傷病(補償)年金受給者のうち第1級の者または第2級の精神・神経の障害および胸腹部臓器の障害の者であって、現に介護を受けている方には、介護(補償)給付が支給されます。
2 使用者に対する損害賠償請求(労災民訴)
(1)労災保険のみでは十分な損害の回復ができない
労災保険では、慰謝料の支払いがなされないばかりか、休業損害等の損害についても満額での支給もなされません。
そのため、労災事故の場合で、かつ、使用者に法的責任が存する場合、使用者に対する損害賠償請求を行い、損害の回復を図る必要があります。
(2)安全配慮義務とは
使用者は、労働者に対し、安全配慮義務を負っています。
具体的な内容は、労働者が労務提供のため設置する場所、設備もしくは器具等を使用し又は使用者の指示のもとに労務を提供する過程において、労働者の生命及び身体等を危険から保護するよう配慮すべき義務といわれています。
さらに、現在、労働契約法5条で安全配慮義務が明記されています。
安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求が認められるためには、①会社に安全配慮義務違反があること、②損害の発生、③安全配慮義務違反と損害との間の因果関係の存在の要件を満たす必要があります。
使用者に対する損害賠償請求を行う場合には、安全配慮義務違反の主張立証を行分ければならないほか、損害額を算定した上で請求しなければならない等専門的な判断を要します。そのため、労災事故でお悩みの方はまずはご相談ください。